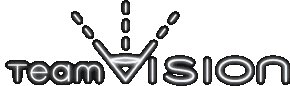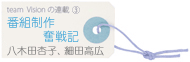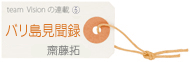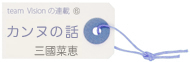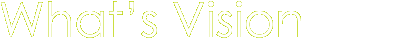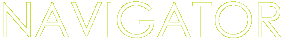二十歳のころ 西原理恵子
笑うのではなく、笑い飛ばす。
西原理恵子のマンガを読むと、腹の底から力がわく。
19の時、上京。
手もとの100万円は、自殺した父が残した140万円から
母が娘に託したお金だ。
一銭たりとも無駄にできないそのお金で、美術の予備校に通う。
何をやっても落ちこぼれだった西原が、絵の道を選んだのは、
絵だけがかろうじて普通のレベルだったから。
翌年、火事場の馬鹿力で美大に合格。
才能もプライドもなかったおかげで、在学中からエロ雑誌のカットを描く。
絵の具を買うためにミニスカパブでバイト。
腹が立っても笑顔でいたら、顔面麻痺になった。
そんな二十歳のころをセキララに描いた「上京ものがたり」。
最後のページにこんな言葉がある。
つぎはなにをかいたら しんどい人はわらってくれるかなあ
失敗も修羅場も、ネタにしちゃえばガハハハ。
西原のマンガは、たくましくて、あったかい。

二十歳のころ 筆談ホステス
筆談ホステスこと、斉藤里恵。
青森から銀座にきて2年でナンバー1となる。
耳が聴こえない彼女の会話は、すべて筆談だ。
人工内耳を埋め込んでみたものの
激しい頭痛に悩まされ、
結局、音のない世界を選択したのは
二十歳になろうとするときだった。
ある客が「辛い」という字を書けば
横線一本足して「幸せ」に変え、メモをわたす。
辛いのは幸せになる途中ですよ。
音のない言葉は、耳ではなく、胸に響く。