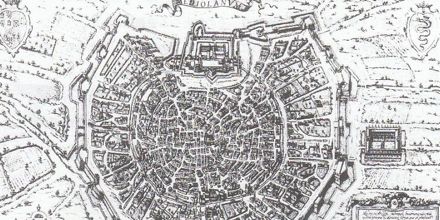
センセイとわたしとナイフ
わたしは毎日、ナイフで鉛筆を削っている。
いまどき鉛筆。しかも、ナイフ。
わたしがつとめるK建築設計事務所ではパソコンを禁じられていて、
図面は手描きだ。そして、所員全員の製図用の鉛筆を削るのが、
わたしたち新米の仕事なのだ。
「ものづくりは、手を動かすことや。パソコンに頼るようなやつらは、
頭の中までゼロイチで奥行きがない」というのがセンセイの言い分で、
「K事務所といえば鉛筆」というのが半ばトレードマーク化している。
世間的には、反骨の建築家ゆえのポリシーということになっているのだが、
単にケチなだけではと所員達はうすうす勘づいている。
わたしたちは、センセイが有名になってからのことしか知らないのだけど、
それまではなかなかに大変な人生だったようだ。
競馬の予想屋をやりながら独学で建築を学んだものの、
学閥と縁がないので設計の仕事はなかなかできなかった。
みかねた田舎の親戚がたまに家の改装を頼んだりすると、
かやぶき屋根の家を総ガラス張りにして出入り禁止なったりしていたらしい。
うけを狙ってもいまいちぱっとしないセンセイのキャリアに転期が訪れたのは、
50代半ばだった。サイドビジネスのクワガタの養殖が大失敗し、
ドン底状態のやけくそでつくった作品――リアカーの上に、
段ボールを張ってつくった移動式住居――が
意外やヨーロッパで高く評価されてしまったのだ。
「システムとしての都市文明に対抗する運動体、
すなわち《個=ノマド》を表象している」とかなんとか。
「いや、ホームレスになってもそれで暮らせるかな思(おも)ただけで。
ついとったわ」とセンセイはよく宴会でもらしていた。
(ちなみに宴会の会費も、割り勘である。)
いざ海外から評価がえられると、エラいもので日本での評価もうなぎのぼり。
設計依頼があれよあれよと舞い込んできたらしい。
お金とか名声のにおいがするところにはますます仕事も人も寄ってくる。
まあ、わたしもその一人だったわけだ。
ここ数年のセンセイの勢いはすごかった。
段ボールが専売特許となり、段ボールハウスは段ボールメゾン、
段ボールレジデンスへと進化を遂げ、ついには段ボールシティ、
というプロジェクトまで動き出した。
事務所の仕事が増えると、センセイの仕事は段々雑になった。
アイデアスケッチをだすこともなく、所員が描いてきた図面に最後、
気合い一閃サインを入れる――というパターンが多くなった。
段ボール建築についての取材はひっきりなしだった。
火事に弱いのでは?とインタビューで問われると
「生きるということは、そもそもリスクを負うことですわ。
段ボールに住まうということは、その根源的なリスクを、
文明社会に取り戻すことを意味するんです」と
もっともらしいこと答えていたセンセイだが、
心配ごとはだいたい実現するもので、
この段ボールハウスの一軒が火事で全焼し、死傷者が出た。
基準をクリアしていたはずの耐火性能に、
そもそも計算ミスがあったことがわかったのだ。
センセイは一転犯罪者扱いされ、バッシングをあびた。
いちばんよくなかったのは、釈明しようとして開いた記者会見で、どう責任をとるのかと問い詰めてきた記者に向かって「戦後の焼け跡から復興した日本人なら大丈夫です」とわけのわからない答えをしてしまったことだ。これがダメ押しになった。
当然ながら建築依頼は激減し、事務所員も次々に逃げた。
わたし?
わたしは、出て行かなかった。なぜかと言えば、
まあ、仕事も身についていないし、
ほかで雇ってくれるところもなさそうだし。
あと、このどうしようもないセンセイの行く末を見届けたいという思いもあった。
そんなわけで、今でもわたしはセンセイと二人きりの事務所で、
誰も使わない鉛筆を削っている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
という文を日記に書いてから何日かたった、ある朝。
小雨が降る中事務所にたどり着いたわたしがドアを開けると――
さりさり、さりさり、という音が奥から聞こえてきた。
見ると、センセイが所員のデスクで鉛筆を削っている。
真黒なクマができた顔で、わたしを見たセンセイは小さな声で
「おお。はやいやないか」
とだけ言うと、またさりさりと、鉛筆を削る。
ぱき、と音がして鉛筆の芯が折れた。
下手だ。もう何十年も自分で鉛筆なんて削っていないのがわかる。
「お茶でも淹れましょうか」とわたしがいっても、センセイは答えなかった。
窓の向こうの、雨で輪郭がぼやけた町をじっと見ている。
「初心に戻ったら、なんか出てくるかな、と思たけど――あかんわ」
センセイがぼそりとつぶやき、鉛筆とナイフをごとりと置いて、席を立った。
デスクの上には、コピー用紙が一枚。真っ白な紙に一行だけメモ書きが見えた。
「段ボール」という文字から矢印がひかれ、その先に「ラップの芯」と書かれている。
センセイはふらふらとドアに向かった。
ドアノブに手をかけたところで、
「ああ、そや」
と、こちらを振り返らないままで言った。
「きみ…もう、鉛筆、削らんでええで」
「いいんですか」
「そんなもん、パソコンでやったらええねや。アホやな」
そう言ってセンセイは、出て行った。
それが、わたしとセンセイが交わした最後のことばだった。
何日かはわたしも事務所に顔を出したが、センセイが帰る様子はない。
センセイが置きっぱなしにした携帯も、しばらくは鳴りまくっていたが、
やがて音をたてなくなった。わたしも事務所に行く理由がなくなってしまい、
家事手伝いの生活に戻った。
そうして今また自宅の机でこれを書いている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
時折、あの事務所の日々が思い出される。
結局のところ、あの頃は今よりよく笑っていたような気がする。
わたしは、センセイが嫌いじゃなかったのだ。
ケチでうさんくさいおっさんなのだけど、でも、見ていて飽きない人だった。
建築なんてものに手をださず、
地道にクワガタの養殖をやっていたほうがよかったのかもしれない。
どうしているんだろう。
あの、段ボールを張ったリアカーで街をさまよっているんだろうか。
そう思うと、センセイが少し可哀想になった。
と、ここまで書いて、聴きなれたダミ声がテレビから聞こえてきた。
思わず振り向くと、「石釜ハンバーグ」という
ファミレスの新メニューのテレビコマーシャルに、
センセイが出ているではないか。
ドリフのコントみたいに顔中真っ黒に塗ったセンセイが
「とことん焼いたれ!」というきめゼリフをシャウトしていた。
わたしは持っていたコーヒーのカップを落としてしまい、
ふとももにわりと大きなやけどをした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、YouTubeの制限時間もあることなので、今日はここまで。
センセイがその後「人生丸焼け建築家」として
テレビのバラエティで華麗な復活をとげ、都知事選に勝利するまでの話は、
また別の機会に書きたいと思う。
出演者情報:西尾まり 30-5423-5904 シスカンパニー
