
遠藤守哉のご挨拶
秋になりました。
というか、秋を通り過ぎ冬に突っ込みそうな勢いです。
秋ってこんなに駿足で勢いよかったでしたっけ。
枯れ葉に涙する、とか
赤く色づいた木の実を掌に乗せてじっと眺める、とか
肌寒い夜に一匹だけ鳴くコオロギに寂寥を感じながら
燗酒を飲む、とか。
そういう季節はどこへ行ったのでしょう。
あれもこれも吹っ飛ばして
半袖をしまう暇もなくセーターを引っ張り出しています。
秋って忙しい。
オリオン座流星群も見損ないました。
それではまた。
![]()

遠藤守哉のご挨拶
秋になりました。
というか、秋を通り過ぎ冬に突っ込みそうな勢いです。
秋ってこんなに駿足で勢いよかったでしたっけ。
枯れ葉に涙する、とか
赤く色づいた木の実を掌に乗せてじっと眺める、とか
肌寒い夜に一匹だけ鳴くコオロギに寂寥を感じながら
燗酒を飲む、とか。
そういう季節はどこへ行ったのでしょう。
あれもこれも吹っ飛ばして
半袖をしまう暇もなくセーターを引っ張り出しています。
秋って忙しい。
オリオン座流星群も見損ないました。
それではまた。
![]()
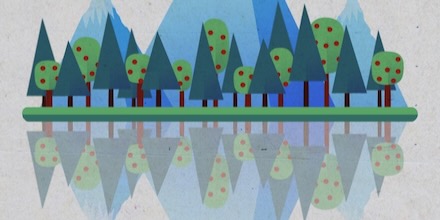
「価値はアート化する」
こんばんは。静かな夜をお過ごしでしょうか。
日本で唯一の、現代アートのラジオ通販番組、
“アート・ビート・ショッピング”です。
お時間の許す限り、お付き合いください。
今宵、ご紹介するのは、こちらのアートです。
作品名は『さわやかな右足』。
制作者は、イスラエルを拠点に活動する、
アリエル・レヴィ。多くを語らない芸術家です。
この作品もまた、多くを語りません。ただ、そこに在るだけです。
しかし、その静けさの中に、私は、計り知れない可能性を覚えます。
どのような形をしているのか、想像してみてください。
はい。今、あなたの頭の中に浮かんだ、その形。
それは、あなたの希望です。
もう少し、言葉にしてみましょう。
高さは、およそ50インチ。
しかし、これは、あくまで見かけ上の数値です。
見る者や、その日の湿度、気圧によって、わずかに、そして確実に、
そのサイズは変動します。
この作品は、「不確かな物質」で構成されているため、
静止しているようで、常に揺らいでいます。
これほどまでに儚く、美しい存在を、私は知りません。
透明でありながら、無色ではありません。
その内部には、光のグラデーションが凍り付いたように存在しています。
最も低い部分に、わずかに深い青色。
しかし、この色は青色ではありません。
これは、「ブルーの観念」が、物質化されたものです。
そして、中央にかけて、徐々に薄い紫色、淡いピンク色、
そして、最も上部には、燃えるようなオレンジ色へと変化していきます。
これらもまた、色そのものではなく、
それぞれが「紫の観念」「ピンクの観念」「オレンジの観念」です。
まるで、時間の流れそのものが、
ひとつの物体として凝縮されたかのようです。
初めてこの作品を見た時、
私は、この夕暮れ色のグラデーションに絶句しました。
この作品には、見る角度によって、微かな動きが見て取れます。
その内部を、無数の小さな粒が、静かに上昇していくのがわかります。
これは、かつて、遠い異国の地で、
ある一人の人間が、黄昏の時間に呼吸した、
その「空気の記憶」が、粒子となって再現されているのです。
私は、その空気の記憶が、
今、目の前で、再び形を得ていることに、深い感動を覚えます。
もし、あなたがこの作品に触れることができたなら、
それは、物理的な接触ではありません。
これは、「物質と記憶の境界線」に触れる体験です。
ひんやりとしたガラスのような表面の下に、
かつて存在した、かすかな温もりを感じるかもしれません。
それは、その日、水面に反射した光が、微かに残した熱なのです。
なんと詩的で儚い存在でしょう。
あぁ、言葉にすればするほど、
この作品の本当の魅力がこぼれ落ちてしまう!
これはただのオブジェではなく、
時間と記憶を、手に取れるようにした、ひとつの「独裁者」なのです。
そして、この試みは、この圧倒的な夕暮れ色によって、
見事に成功していると、私は思います。
この作品を所有することは、
あの日の夕暮れを、あなたの意識の中に、永久に定着させることでしょう。
さあ、この『さわやかな右足』という素晴らしい作品、
お値段は、特別に120万円です。
お求めになられる方はいつものフリーダイヤルにお電話ください。
ではまた、静かな夜を。
.
出演者情報:清水理沙 アクセント所属 https://aksent.co.jp/profile/shimizu_risa/
![]()

夕暮れ
晴れでもなく、曇りでもなく、
暑くもなく、寒くもなく、
昼でもなく、夜でもない。
人がいるわけでもいないわけでもない。
住宅街を歩いている。
目的があるわけでも、ないわけでもない。
ただなんとなく歩いている。
なに食べる?と聞かれる。
魚でもいいし、お肉でもいい。
洋食でもいいし、中華でもいい。
はっきりしない男だね、と怒られる。
はっきりしない男の好きな季節は、
北海道の8月お盆明けから、10月の初雪が降るまでの季節。
あと東京の5月が好き。
それって結局どの季節が好きなの?と聞かれる。
さっきも言ったけど、と同じ話をする。
馬鹿を見るような目で見つめられる。
向こうから30代にも60代にも見える男が歩いてくる。
男はタンクトップを着ているわけでも着ていないわけでもない。
タンクトップは生地が伸びきっていて
左右の乳首が丸見えになっている。
見るわけでも見ないわけでもなく、
ただ視界に入れながらすれ違う。
あれって露出狂なのかな?と聞かれる。
見る人によるね、と答える。
ゼロか100か。
白か黒か。
子供か大人か。
男か女か。
敵か味方か。
生きるか死ぬか。
はっきりしないものは存在しないことにされる。
わかりやすいことが必要とされる。
イエスかノーかで答えることが求められる。
主張の強い人間たちだけが生き残る。
季節は春や秋がなくなり、
夏と冬だけになっていく。
気づくと昼と夜だけになり、
夕暮れもないものになっていく。
晴れでもなく、曇りでもなく、
暑くもなく、寒くもなく、
昼でもなく、夜でもない。
そんななかを歩いていく。
出演者情報:大川泰樹 03-3478-3780 MMP所属
![]()

夕刻
ストーリー:蛭田瑞穂
出演:遠藤守哉
「ワインをお注ぎしましょうか」
ミシマは頷き、グラスを差し出した。
カフェ・ド・フロールのテラスで、
冷えたシャブリが注がれる。
その透明な液体は、夕陽を受けて黄金の輝きを宿した。
パリの空は燃えていた。
沈みゆく太陽が空一面に敷き詰められた無数の鱗雲を、
朱から紅へ、紅から茜へと染め上げ、
巨大な龍が天を覆うかの如き壮観を呈していた。
夕陽は何故かくも美しいのか。
朝陽は希望という名の幻想に彩られているが、
夕陽は何も約束しない。
ただ終焉を、漆黒の闇をもって宣告する。
美とは喪失であり、喪失こそが美の源泉である。
薔薇が永遠に咲き誇るならば、誰がその花弁に陶酔しようか。
恋も青春も、終焉という名の断崖を前にしてこそ、
最も激しく燃え上がる。
この夕陽と共に、すべてが幕を閉じるならば、
—— ミシマはシャブリを一口含んだ。
それは完璧な終幕ではないか。
世界が最も美しく輝く瞬間に、最も美しい形で完結する。
夕陽という巨大な幕が降りて、その幕は永遠に上がらない。
コクトーは言った。
「詩人は永遠の眠りについてから生き始める」
何という逆説。
何という真実。
生きている詩人は、詩人の仮面を被った俗人に過ぎぬ。
詩人の真の誕生を告げるのは、
墓石にその名が刻まれた時である。
喪失の刹那にこそ、美は絶頂に至る。
散る桜も、流星の煌めきも、沈みゆく夕陽も、
すべては失われる瞬間に、
その存在の極致を最も純粋な輝きとして顕現させる。
故に、私は死を恐れぬ。
死とは、美の究極の完成、否、その唯一の実在である。
私はそれを、生まれる前から知っていた。
.
出演者情報:遠藤守哉
![]()

夕暮れ
「案外時間ないんだよね」
最近のクンペイの口癖だ。
それはたとえば二人が食事をしている時、
映画が始まるまでまだ十分時間はあるのに、
クンペイは時計を見るとせわしなく立ち上がってレジに向かう。
「急がないと」
あわてて後を追いかけながら、わたしは少しさびしい気持ちになる。
「コーヒーぐらい飲みたかった」
「映画館に着いてから飲めばいいよ。その方がゆっくり飲める」
その考え方だ。間違ってはいないけど、正しすぎるところがいやだ。
最近クンペイは変わった。
高架下の暗がりに、一匹の子犬がいて、寒そうにふるえていた。
「この子、迷子かしら」
わたしが立ち止まると、
何やってんだ、という風に肩をすくめて、腕時計を見る。
「案外時間ないんだよね」
小さい声でぶつぶつつぶやいている。
その息が白い。
夕暮れ時になると、空気が急に冷えてくる。
今夜は0℃近くまで下がるだろうと天気予報では言っている。
まだ9月だというのに。
寒い夏が終わり、これからもっと寒い秋が始まる。
季節の名前なんてもう意味がないのかもしれない。
世界中で気温が下がっている。
地球寒冷化という言葉を耳にするようになったのは去年の夏だった。
それが事実であることをもう疑う人はいない。
世界中でホームレスや貧しい人が凍死している。
少数の大国が石油やLNGを独り占めしている。
日本のエネルギー不足は深刻だ。
夜9時には電気の使用が禁じられている。
街の灯りは消えた。
飲食店は夕暮れとともに店を閉める。
デパートは休業状態。
映画館や娯楽施設は多くが営業を自粛した。
銀座で1軒だけ、細々と上映を続けている映画館がある。
観客たちは飢えた子どものように映画が始まるのを待っている。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。
クンペイが抽選でやっと手に入れたチケットだ。
陽気な音楽が始まると、人々はスクリーンに見入る。
最初はおずおずと、そのうち安心したように笑う。
映画を見ていると、以前と変わらない日常が外で続いているような気がする。
けれども、9時になる前に上映は打ち切られ、
観客たちは灯りの消えたエントランスから人目をはばかるように外に出る。
そして現実に戻されるのだ。
銀座の街は真っ暗で、まるでゴーストタウンのようだ。
人通りの少ないみゆき通りを歩いていると、向こうの方で赤い火が見えた。
誰かが焚き火をしているようだ。
店をたたんだ店主がテーブルや椅子などを持ち出し、
道ばたで燃やしているのだった。
火のまわりには、通りすがりの人が立ち止まって
手を差し伸べて暖を取っている。
クンペイもわたしも中に加わった。
おじさんたちが見知らぬ同士で言葉を交わしていた。
「ついこの間まで異常気象で暑い暑いって言ってたのにな」
「そうだった。暑くて溶けそうだった」
「それがなあ。同じ異常気象でもまさかこんなことになるなんて」
「地球が狂っちまったんだなあ」
火の中で椅子の脚がパチパチとはぜる。
「R国が北海道を狙って攻めてくるってね」
「少しでも暖かい南へってわけか。
石油と引き換えならちょっとくらいわけてやってもいいぜ」
「おい」
「いや冗談だよ」
それっきりおじさんたちは黙ってしまった。
外国の侵略の動きに抗議する声がSNSを騒がせている。
実力で阻止しようと呼びかけるグループもある。
クンペイがわたしに言った。
「案外時間ないんだよな」
わたしは時計を見た。
10時の終電を逃したら帰れなくなる。
わたしたちは焚き火を離れ、真っ暗な道を駅の方へ歩き始めた。
世界がこんなに心細いものだとは知らなかった。
地球はこのまま冷えて行って、
冷たい命のない星になってしまうのだろうか。
その上にいるわたしたちも死んでしまうのだろうか。
残された地球のわずかな温もりを奪い合いながら。
「世界は元にもどるの?」
その時、雪が降ってきた。
クンペイは黙って黒いビルの空を見ている。
わたしも空を見上げる。
「案外時間ないんだよね」
クンペイのその言葉には絶望の響きがあって、わたしはふるえた。
「根室沖は軍艦がいっぱいだってさ」
「世界は元にもどるの?」
もう一度聞いた。
「アカネ」
クンペイはわたしの名を呼んだ。
「明日はどうなるかわからない。
わかってるのはそれだけだ。
ぼくたちには、案外時間がない」
駅に近づくと、終電に乗り遅れないように駆け出す人の姿が見えた。
わたしたちも走った。
別れる時、クンペイが言った。
「明日ぼくは北海道に行く」
日本の歴史上最も寒い秋が過ぎ、冬が過ぎ、暦の上では春になった。
テレビのニュースは増え続ける凍死者の数を伝えている。
根室沖では流氷が消える気配はなく軍艦を閉じ込めている。
あれ以来クンペイは北海道から帰ってこない。
明日になったら、わたしも北海道に行こうと思う。
クンペイと会えるかもしれない。
わたしはまだ生きている。
時間はまだある。
.
出演者情報:清水理沙 アクセント所属 https://aksent.co.jp/profile/shimizu_risa/
![]()

ハルヤマさんの夢コピー
ハルヤマさんは先輩コピーライター。机に
頬杖ついて、何か深刻そうに思い悩む風だっ
たので、「海辺、行きます?」声をかけたら
ピョンと立ちあがった。黙ってスタスタ出て
ゆく。ハルヤマさんは天才的だからそういう
変なところはある。おかげで僕のほうがあわ
てて追いかける羽目になった。
広告会社は厚生年金会館の裏にあって盛り
場が近い。ハルヤマさんは小柄ながら歩くの
が速い。きょうはことに速い。靖国通りを浮
き滑るように行く。僕のほうが十も若いのに
追いつくので精一杯。
「待ってください、ハルヤマさん」
「あっ、そうかあ」
ハルヤマさんは僕の存在にはじめて気がつい
たように言った。
空は夕方の光が残って夢のよう。みんなビ
ルの上の空が好き。きょうハルヤマさんの足
が逸るのも、きっと僕同様うれしくなっての
こと。
と思ったら、目の前を赤い巻きスカートの
女が行く。早足のせいで追いついたのだが、
巻きスカートの腰の淫らな曲線を目にするに
つけ、ああ、ハルヤマさんの早足はこっち目
当てだったんだと、疑り深い僕はたちまち疑
った。
と、女は通りがかりの花園神社へ入ってい
かなかった。女を追いかけて神社を通過しち
ゃう!と僕が危ぶんだハルヤマさんは、九十
度の角度できっぱり境内へ道を折れた。ゴー
ルデン街へは花園境内を経由して行くべしを、
ハルヤマさんは迷いなく実行した。僕は赤面
したのを隠した。
海辺の憂鬱はとっつきの路地の二階にある。
つくりは通り一遍のカウンターバー。お定ま
りのジュークボックスが店内をよけい窮屈に
している。このどこが海辺なんだろう。
ハルヤマさんはいつものようにナントカの
アイルランドのウイスキーを満たした小さな
グラスを手にした。
「あっ、そうかあ、もう負けた負けた、やめ
よかな、彼らの言う通りだもの」いつもの甲
高い声で言った。
彼らというのは地元の商店会の人たち。ホ
ラきた、と僕は思った。ハルヤマさんが机で
悩んでいたときから、男は、で始まるあのコ
ピーだとわかっていた。
「あっ、敢えてでしょ、ぜんぶ敢えて、敢え
て男で、敢えて黙るで、敢えてすぎ!」
ハルヤマさんは、まるで喜々としてかのよ
うに、じぶんを傷つけはじめた。そうなると
止まらない感じで。
「私どものビール祭りなんて、折り込みチラ
シだけのささやかなもんで、男も女もなくて、
あっ、ビールでも何でもよくて、とにかく賑
やかにしてほしいんです、って、その通り!
そりゃそうだ!」
僕は少しいらいらした。ハルヤマさんのコ
ピーが良くないわけがない、今回のビール祭
りのも完璧だった、わかってないのは商店会
の連中にきまっている。
思わずしゃべっていた。
「男すぎたっていいんです!それは腹をたて
た女を呼ぶんです!お祭りです!」
するとハルヤマさん、ふと熱を帯びて、
「新宿が騒がしいでしょ。フーテンとヘルメ
ットだらけでしょ。天変地異がもう始まって
るんだよ。新宿のコピーは、そういう騒がし
さに合わせないと…あっあっ、でも没!没!
没コピー!」
ジュークボックスからひどく古い歌謡曲が
流れる。ハルヤマさんは二杯目のウイスキー。
「リルはリトル、上海のリトルな女の子」
僕は訊いてみたかった質問をした。
「あんな凄いコピー、どうやって思いついた
んですか?」
「あっ、降りてきた…降りてきたからしょう
がないよ…」
「あれ、いいコピーすぎます。いいコピーす
ぎるよ」少し涙ぐんだ。
同時に、没コピーは船に乗って海をさまよ
う、と変なこと思ったが、恥ずかしく黙って
いた。
出演者情報:大川泰樹 03-3478-3780 MMP所属
![]()