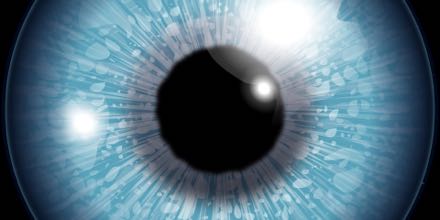水を売る
ストーリー 直川隆久
出演 遠藤守哉
水って、基本じゃん?
人間の体は90%水でできてるわけだからさ。
飲む水が悪いと、悪い体になるし、
いい水を飲めば、いい体になるんだよね。
っていうと、ほら、あるでしょ?
水素水っていうのが。
水素が入った水。
すごい、はやったじゃん。
でも、じつは、もっとすごいものがあるの。
水素よりもっとすごいもの。
わかる?
それって、元素なんだよね。
元素。
元素だよ。
きいたことあるでしょ?
元素は大事なの。
元素はいいんだよ、体に。
元素って、みんな言葉としては知ってるんだけど、
その本当の力を知らないんだよね。
元素ってのは、元気の素って、書くじゃん?
つまりさ、元素が足りなくなると、元気が足りなくなるの。
だから、じつは、イオンなんかより、ずっと元素のほうが重要なんだよね。
むかしの人はね、体の中に元素をいっぱいもってたんだよね。
それがね、現代人は、体の中の元素が少なくなってるんだって。
それって、なんでかわかる?
これ、おれもすごいびっくりしたんだけど…「感謝」なんだよね。
昔の人はね、いろんなことに感謝してたんだ。
太陽、ありがたいなあ。
雨、ありがたいなあ。
ごはんが食べられる、ありがたいなあ。
で、じつは、感謝をすると、人間の脳内である変化がおきんのね。
脳内ホルモンのセロトニンていうのが出るの。
これが、体の中の元素を活性化させるんだよね。
ところが、おれを含めて現代人って、
昔の人とくらべて、感謝をしなくなってるじゃん?いろんなことに。
今は、みんなさ、「わたしがわたしが」「権利が権利が」でしょう。
つまり、自分のことばっかりで、感謝がないんだよね。
そうするとどうなるかっていうと、
脳内ホルモンのセロトニン、これの分泌が減るのね。
で、セロトニンが減ったことによって何がおきるかっていうと、
体の中の元素がね、一酸化元素、っていうのに変化するのね。
この一酸化元素が、じつは、すっごい悪さをするのね。
一酸化元素は、おたがいに、ひきよせあっちゃう性質があるんだ。
アメリカのカリフォルニア大学の研究で明らかになったことなんだけど、
癌細胞の中には、通常の細胞の100倍の一酸化元素があるんだって。
つまり、癌細胞の中の一酸化元素が、ほかの癌細胞を呼んで、
どんどん癌が大きくなっちゃう。
それだけじゃなくて、これは、カーネギーメロン大学の研究で
明らかになったんだけど、
社会的に成功しなかった人の血液の中には一酸化元素が多いんだって。
これは、貧乏の人の一産化元素が、
ほかの貧乏な人をよびやすいせいだろうと言われてるの。
だからこのことによって得られる結論は、一酸化元素が多い人は、
癌にもなりやすいし、貧乏にもなりやすいっていうことなんだよね。
で、開発されたのが、この元素水なの。
元素を、水の中に閉じ込める技術ってのがアメリカで3年くらい前に開発されて。
この元素水っていうのはね、
すっごい、新鮮な元素が入ってるんだって。
いや、もう、すごいらしいんだ。
とにかく、もう、AIでも数えられないくらい元素が入ってるんだって。
これは、飲む価値あると思うんだよね。
毎日この元素水を3リットル飲むと、体の中に、元素が凄く増えるんだって。
おれ、これを飲み始めて、すっごい変わった、と思う。
うん、まず、肝臓の数値が下がったのと、
あと、水虫がきれいになった。不思議なんだけど。
あとね、宝くじに2回当たった。
それも、結構大きな金額。
これも、元素水のせいかなあ、って思ってるんだよね。
で、話きいてみてどう?
なんか怪しいなって思う?
そう。
いや、そうなんだよ。
実際信じられないのは、無理ないと思う。
おれもそうだったもの。
ネット調べても、一酸化元素なんてでてこないしさ。
だから、最初この元素水を先輩から勧められたときも、かなり疑ってたのね。
でもさ、ふと思ったんだよね。
疑うだけじゃ、何も変わらないし、成長もないよね?
だから、おれは、自分で飲んでから判断しようと思ったのね。
それで、一か月飲んでみたの。実際に。
そしたら…飲んでるあいだに、あれ、けっこう、いいこと…あるじゃん?みたいな。
悪いこと、ないじゃん?みたいな。
で、ふと思ったわけ。
飲んで悪いことあるんなら、やめたらいいんだけど、
今のとこないし、それで続ける理由としては十分じゃないのかな。
で、今まで飲み続けてる。
そんな感じ?
だからお前も、自分で判断してほしいんだ。
やっぱり、自分の納得っていうのが、一番だもん。
あ、そう、飲んでみたい?
…うん。ぜひ、飲んで飲んで。きょう、持ってきたんだよね。
どう?
なんか、すごい…やわらかいでしょ。
ね?
なんか、すーっと…すーっと、こう、入ってこない?
浸透圧的なあれが、けっこうあるみたいなんだよね。
うん。
おれはね、いろいろ言ったけど、単純に、おいしいから飲んでる?そんな感じ。
で、この元素水って、まだ日本の代理店がなくて、
アメリカから直で買うしかないんだけど、
1リットル入りのペットボトルで一本1,000円とかすんのね。
でも、それってむずかしいよね?
一日3リットル飲まないといけないわけだからさ。毎日、3,000円だもん。
で、そこでちょっとこのパンフレット見てほしいんだけど、
元素水サーバーっていうのを使えば、水道の水を元素水に変えることができんのね。
これが、今、80万円で販売中…
なんだけど、
なんだけどね。
おれ、実はここのサーバーを製造してるアメリカの会社の
エグゼクティブ・アンバセダー資格っての持ってんのね。
だから、日本の一般の会社には卸せないこのサーバーを、
特別に会員価格で支給してもらえるの。
1台、32万5,000円。
どうかな。
高い?
うん。だけど、でも、これは一生使えんのね。
ていうのは、このサーバーは空気から元素をつくるから。
だから、必要なのは、水道水だけなの。
かかるのは、電気代と水道代くらい。
うん。
もちろんもちろん。
破格の割引とはいえ、やっぱり、金額的には大きいからさ。
ゆっくり考えて。
いやあ、でも、おまえと今日話せてよかったよ。
10年ぶり?
これって、ひょっとしたら元素水がひきよせてくれたのかもしれないよな。
で、話をきいてくれたお礼にさ。元素水の、20ケース、プレゼントさせて。
届けるから。宅配で。
いいのいいの。
こうやって今日、おまえと話せたことへの感謝のしるしだから。
それを飲んだ上で、おまえの答え、きかせてほしいんだよね。
うん。
じゃ、ここに住所書いて?
たぶんね、3日以内には着くと思う。
うん。
いや、今日はほんとどうもありがとう。
これから、また、長い付き合いしていこうぜ。
出演者情報:遠藤守哉(フリー)



![]()