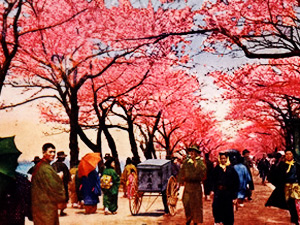o_Ozzzzk
記録のはなし 澤穂希の記録
6回のワールドカップを経験したサッカー選手、澤穂希。
彼女の功績はFIFA女子ワールドカップ最多出場選手
としてギネスに登録されている。
そんな彼女もサッカーを辞めよう
と本気で思ったことがあった。
1990年代に日本のプロサッカー部が次々廃部を決める中、
澤は思い切ってアメリカに渡る。
「クイック・サワ」と呼ばれ大活躍する中で、
あるアメリカ人と恋に落ちた。
彼と一緒に暮らしながら、サッカーに全力投球する充実した日々。
しかし、突然、プロリーグが休止することになった。
この時、澤は恋人と結婚してアメリカで暮らそうと決意する。
恋人の、「サッカーやめられるの?」
という問いに「もちろん」と答えた。
すると恋人は意外な言葉を返した。
「きみには、とことんサッカーをやってほしい。」
澤はそのひと言に背中を押されて、
再び日本のプロサッカー界へ戻ってきた。
ひたむきな生き方、
それが彼女に多くの記録をもたらしたのだ。