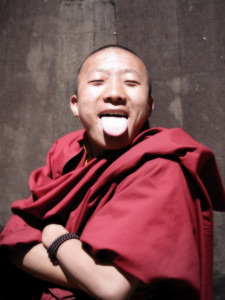karinckarinc
掃除のはなし 親子関係の大掃除
断捨離の提唱者、やましたひでこさん。
彼女の母は典型的なモノを溜め込むひとだった。
それが嫌で、結婚後も実家に帰るたびに
捨てに捨てに捨てていた。
そうするうちに母との関係はどんどん悪くなる。
なぜ母のために片付けているのに感謝されないの?
そう思ったとき
無意識のうちに片付けを通して
母に報復していたと気づいた。
生き方が違うんだなと思えるようになってから
親子関係も修復していったという。
母の前では、断捨離を捨てること。
それは、娘が母から完全に自立できた
親子関係の大掃除だったのかもしれない。