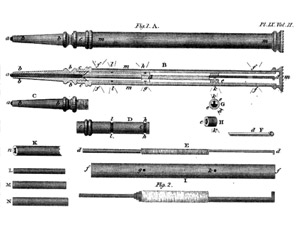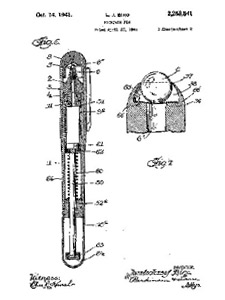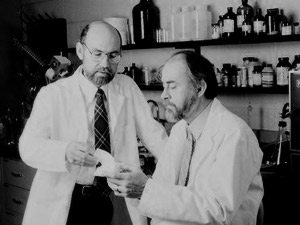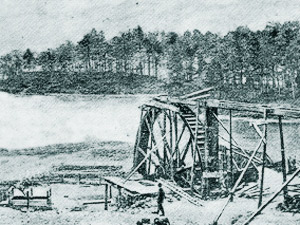
Pedro
文房具のあれこれ 〜鉛筆〜
エリザベス王朝時代の1564年。
イギリスのボローデル山で、黒いかたまりのようなものが発見された。
その黒いかたまりが、現在の鉛筆の芯の原料となる黒鉛だ。
はじめ、人々は黒鉛そのものを手に持って、文字や絵を書いていたが、
手が汚れて使いづらかったため、
木に挟んだり、布で巻いたりして、使うようになった。
こうして、多くの人々が黒鉛を使うようになった結果、
約200年後には、ボローデル山から黒鉛が姿を消してしまった。
そこで、ニコラス・コンテとカスパー・ファーバーは
他の山からとれる黒鉛を細かい粉にし、粘土と混ぜ、焼き固め、
見事に鉛筆の芯をつくりあげたのだ。
また、黒鉛と粘土の割合を変えることで、
芯の濃さを変えることができることも発見した。
黒鉛の使う量を減らすために、生まれたこの方法。
使い勝手も、書き心地も、以前の方法よりよかったため、
今でも、鉛筆の芯は、この方法を基本に作られている。