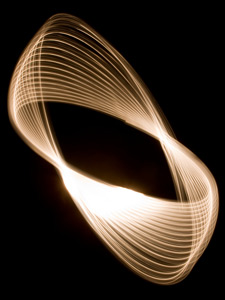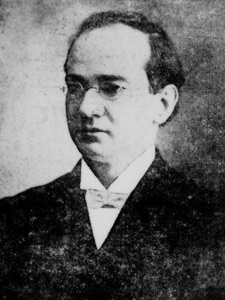時の記念日 体内時計
人は誰でも、体の中に時計を持っている。
日本人の体内時計の平均周期は、24時間10分。
24時間にかなり近いものらしい。
もちろん個人差はあるが、
標準的な体内時計を持っている人は、
自然と規則正しく生活できるというわけだ。
しかし体内時計の周期が長い人は、
気を抜くと夜更かしのほうにずれていってしまう。
逆に周期が短すぎれば早寝早起きになる。
心当たりのある人もいることだろう。
でも社会全体を見れば、
それにはちゃんと意味がある。
夜勤に強い人がいる。早朝から働ける人がいる。
それも社会に必要な多様性なのだ。
私たちは、時計によって
人類共通の時間を手にいれた。
けれどときどきは、
体の中にある自分だけの時計に
意識を向けてはどうだろう。
きょうは、時の記念日。