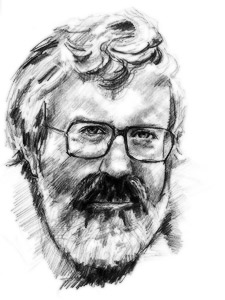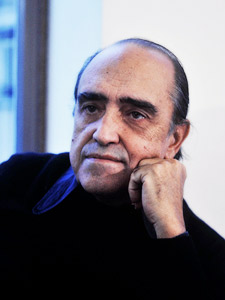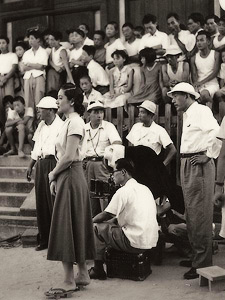葱
寒さの季節に 西郷隆盛と黒田博樹
西郷隆盛は晩年、
親戚の青年に
こんな言葉を贈った。
雪に耐えて梅花(ばいか)麗し
梅の花の美しさは、
雪降る寒さを耐えた先にある。
この言葉、
100年の時を経て、
一人のプロ野球選手の座右の銘となった。
元広島カープ、黒田博樹投手。
高校時代は控え投手だったが
大学で力をつけ広島に入団。
低迷期にあったチームを支え、
メジャーリーグに挑戦。
そして再び古巣に戻り、
日米通算200勝という大きな花を咲かせた
雪に耐えて梅花(ばいか)麗し
今日は大寒。
梅の季節はゆっくり近づきつつあります。