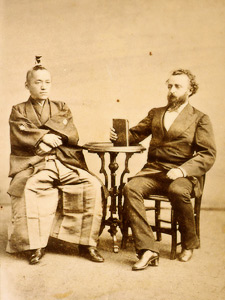1860年3月3日の雪
1860年3月3日。
季節外れの大雪に見舞われたその日、
井伊直弼は、水戸浪士らによって暗殺された。
彼の護衛は五十名を超え、普段であれば負けるはずもない戦い。
ところが雪に備えた重装備であったため
すぐに刀を抜くことができず、わずか十数名の敵によって、
井伊直弼は首を落とされてしまったのである。
知らせを聞いて駆け付けた武士は、そのときの光景をこう語った。
「雪は桜の花を散らしたように血染となっていました。」
桜田門外の変ー。
もしも雪が降っていなければ、歴史は変わっていたかもしれない。