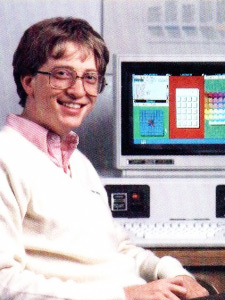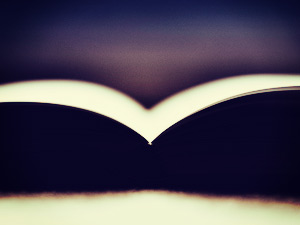Simon Cocks
読書の話 北方謙三
日本を代表するハードボイルド作家、歴史小説家、
そして、数々の文学賞の選考委員でもある北方謙三。
彼が、旅のお供に持っていく本とは…?
旅行に重い本を持っていって、つまらなかったら腹が立つ。
だから、絶対面白いと分かっている本を持っていく。
全部読むわけではなくて、好きなところだけ読むんだけど。
本があるとないとでは人生の豊かさが違ってくると語る北方。
とあるインタビューで、本の読み方を聞かれて、こう答えた。
男だったら流行とは関係なく、
本の背からにじみ出るにおいを嗅ぎとって選ぶんだ
電子書籍やネット小説にはない、紙とインクのにおい。
新しい本にも古本にも、それぞれ独特のにおいがある。
いよいよ、読書の秋。本のタイトルや装丁で選ぶジャケ買いもいいが、
“におい”で選んでみると、運命の一冊と出会える…かもしれない。