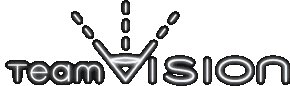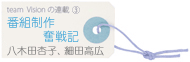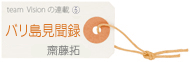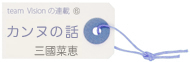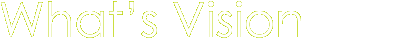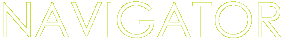蛭田瑞穂 11年5月15日放送

檀一雄の食卓
小説『家宅の人』で知られる作家、檀一雄。
世間には無頼派作家として通っていたが、
食生活に関しては規則正しく、ほとんどの食事は
自分の手でつくっていた。
その腕は文壇随一とも言われ、
『檀流クッキング』というエッセイも書いている。
買い物カゴを提げて商店街を歩くのが
日課だったという檀一雄はこんな言葉を残している。
この地上で、私は買い出しほど、好きな仕事はない。

寺山修司の食卓
寺山修司の食卓はいつも賑やかだった。
劇団「天井桟敷」を主宰していた彼のもとには、
陽が沈む頃になると、その日の夕飯にありつけなかった
劇団員たちが集まってきた。
家出してきた者が土産を持ってくることもあれば、
飲食店を営む劇団OBから、
不意に付届けが来ることもあった。
日ごとに違う人物が登場し、
日ごとに違う風景が繰り広げられた寺山修司の食卓。
彼は言う。
人生同様、食卓もまた劇場である。

澁澤龍彦の食卓
作家、澁澤龍彦。
ジャン・コクトーやマルキ・ド・サドの作品を日本に紹介し、
『高岳親王航海記』などの小説も執筆した。
百科事典的な博学の持ち主として知られ、
その著作は思想から美術、ヨーロッパ文化まで
幅広い範囲に渡った。
彼はまた美食家でもあった。
朝起きると「今日何を食おうか」というのが常で、
その日に捕れる相模湾の魚を心待ちにしていたという。
食に関して澁澤龍彦はこんな文章を記している。
アストロノミーは天文学のことだが、
この言葉の前にGをつけると、
ガストロノミーすなわち美食学となる。
アストロは星の意であるが、ガストロは胃の意である。
私はガストロノミーという言葉を聞くと、
自分の胃のなかで、無数の星が
軌道を描いて回転しているような気がしてくる。
まことに澁澤龍彦らしい表現である。

向田邦子の食卓
向田邦子の少女時代、向田家ではふたつの鍋で
カレーをつくっていた。
大きい鍋は家族用。小さい鍋は父親用。
父親のカレーは辛口で、肉も多かった。
早く大人になって、そのカレーが食べたい。
彼女はいつもそう思っていた。
カレーといえばもうひとつ、
向田邦子にはこんなエピソードがある。
人気ドラマ「寺内貫太郎」の脚本を執筆していた時、
彼女は寺内家の朝食として台本にこう書き加えた。
「ゆうべの残りのカレー」。
下町の家族の暮らしをわずか一行で表現した邦子の感性に
出演者もスタッフも感心したという。

井上ひさしの食卓
井上ひさしは歯医者が大の苦手だった。
虫歯ができても放置し続けたため、
やがて前歯を除くほとんどの歯が虫歯になった。
その痛みに耐えきれず、ある時彼は入院し、
重症の虫歯を一気に13本抜いた。
それ以来、井上ひさしは
やわらかいものしか食べられなくなった。
そんな彼のために、妻は歯に負担の少ない料理をつくった。
ハンバーグと揚げたチーズと
ニンジンを絞ったジュースを井上ひさしは特に好んだ。
彼は妻のつくる料理にこんな感想を述べている。
ただひとつのしあわせは、
家人が世にもまれな料理下手だったということだ。
彼女がもし料理上手だったら、
心をこめて作った料理に渋面を作る夫を、
やがて憎むようになっただろうから。
井上ひさしらしい感謝の仕方である。

遠藤周作の食卓
遠藤周作の家では
夕飯は漬物とあと一品と決まっていた。
毎日の献立を決めるのは妻の仕事で、
彼女には食事は質素をもって旨とすべし
という考えがあった。
周作はたまには贅沢をしたいと思うが仕方ない。
自分の仕事に口を出させないかわりに、
妻の仕事にも口を出さないというのが、
遠藤家のルールだったから。
そう思いながら、遠藤周作は明るく言う。
何はなくても家族みんなでたべる食卓はたのしい。
それはどこの家庭でも同じでしょう。
時々、夢で血のしたたるビフテキを食べている
自分の姿を見ますがね。

齋藤茂吉の食卓
歌人、齋藤茂吉は鰻に目がなかった。
その生涯で1000匹以上の鰻を食べたともいわれる。
太平洋戦争の最中、疎開先の山形で友人から鰻を送られた。
久しぶりに食べる極上の鰻に、茂吉はこんな句を詠んだ。
肉厚き
鰻もて来し
友の顔
しげしげと見む
いとまもあらず

田村隆一の食卓
詩人、田村隆一の晩年、朝食は決まって
妻のつくる弁当だった。
幼い頃から病弱で心臓の手術もした妻は朝が弱かった。
そのため、前の晩に弁当をつくり、
隆一の朝食として用意した。
目ざめると、隆一は弁当を持って2階に上がり、
窓の外を眺めながらそれを食べた。
朝早く、妻のつくった弁当をひとりで食べる。
その時間が隆一は好きだった。
窓の外には美しい鎌倉の海が見えた。
彼は妻の料理の味付けを気に入っていた。
家内の味つけは、
今風の料理屋より数段上です。
田村隆一はことあるごとに友人にそう吹聴していたという。