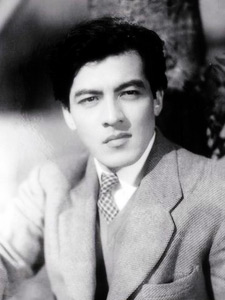鬼が笑った話 初代若乃花
昭和33年。体重105キロの小柄な力士が横綱に昇進した。
初代・若乃花。
熱のこもった取り組みから「土俵の鬼」と呼ばれた男である。
同時期に横綱であった栃錦といくつもの好勝負を演じたため
「栃若時代」という言葉もうまれた。
引退会見で「横綱の豪快な上手投げや呼び戻しが見られないのは
本当に寂しい」と言われて、こう答えた。
『まぁそのうちにまた出てきますよ、そういう人が。』
30年後、甥っ子である貴花田が初優勝。
理事長としてトロフィーを渡すこととなった。
少し険しい顔をして涙をこらえていた土俵の鬼は、
土俵を降りてから静かに微笑んだ。