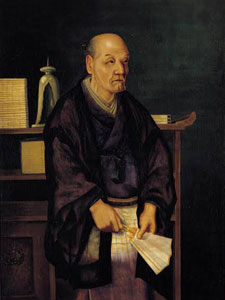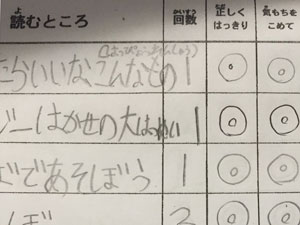Photo by Daniel Sturgess
大地のはなし 大地を深掘りしていくと
大地の成分は、岩と土。
マグマが急速に、あるいは、
ゆっくりと冷やされたことで、できた岩。
生物の死骸が集まり、積み重なって、できた岩。
そんな岩たちが水や風で砕かれたり、
地下の奥深くで強い作用を受けたりして、できた岩。
それら岩石の細かい粒子がベースとなり、
そこに火山灰や、
動物・植物・微生物の死骸と排せつ物、
微生物によって分解された有機物などが
混じり合って、土になる。
土の中にはたくさんのすき間があり、
そのすき間は水と、
二酸化炭素や窒素を多く含んだ空気で満ちている。
たくさんの微生物や、動物たちも生きている。
大地を深掘りしていくと、
はるか宇宙の、
見知らぬ惑星のような風景が見えてくる。