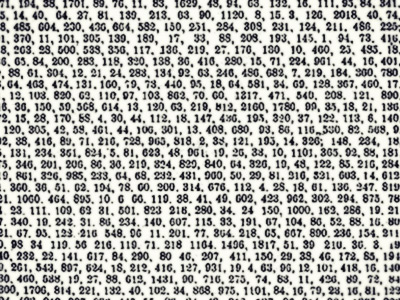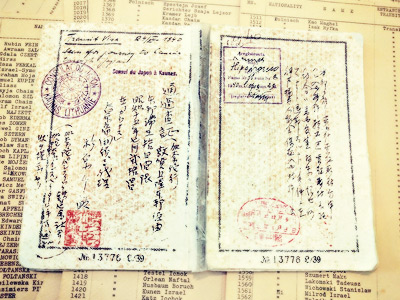oschene
一枚の、楽譜
ヨハン・セバスチャン・バッハ晩年の楽曲集「音楽の捧げもの」に
「蟹のカノン」と呼ばれる作品がある。
正式な曲名は「2声の逆行カノン」だが、
その独特なコード進行が横歩きの蟹を思わせるため、
「蟹のカノン」と呼ばれるようになった。
「蟹のカノン」の楽譜は音符が回文のように並んでいる。
そのため、前後どちらから演奏しても楽曲が成り立ち、
ふたりの奏者が同時に前後から演奏すると素晴らしいハーモニーが生まれる。
さらに、最初と最後の音がつながるため、曲は無限にループする。
一枚の楽譜の中にバッハは無限の創造性を生み出す。