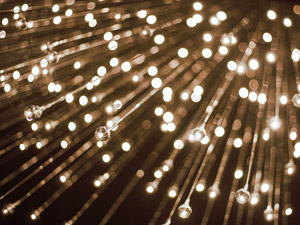お風呂① 杉滝
吉田松陰の母、杉滝。
嫁いだ先は、極貧の武家だったが、
そんな中でも、彼女は「毎日お風呂に入る」と宣言した。
義理の父から猛反対を受けながらも、
「貧しさのあまり心まで貧しくなってしまっては
どうしようもない。
温かい湯につかることで、心まで温もり、
翌日も頑張る意欲が生まれるはずだ」
と言いはり、お風呂に入り続けた。
滝は、子供たちを風呂に入れるのも大好きで、
吉田松陰が安政の大獄で処刑される前、
一日だけ帰宅を許された際にも、
松陰を風呂に入れ、無事の帰りを祈ったという。
風呂から伝わる母の愛は、
松陰の最後の一日を、きっと惜しみなく温めていた。