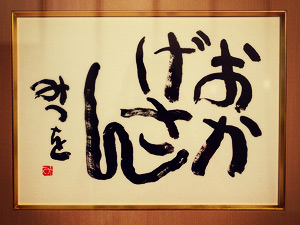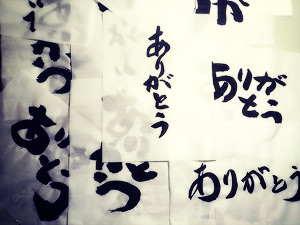風と舟 ジャンク
ジャンクは中国の船。
三本マストに四角い帆を張り、
その帆を竹で補強している構造だ。
はじめは沿岸を走る小さな船だったようだが、
10世紀を超えると「宝船(ほうせん)」と呼ばれる
大型船に発展した。
その大型船62隻の大船団を組み
季節風を受けて東へ船出したのが
中国の明の時代の皇帝に仕える鄭和(ていわ)だった。
鄭和の船団は4度めの航海でインド洋の西に達し、
5度めにはついにアフリカのケニヤに足を伸ばして
シマウマやキリンを持ち帰っている。
鄭和の宝船は、明の記録によると
全長137メートル、9本マスト。
当時としては世界最大の大型船だった。