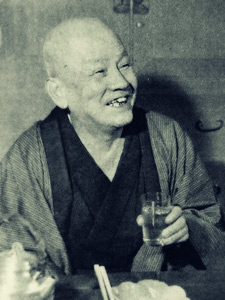義家の勇気
今日は、納豆の日。
納豆の起源には諸説あるが、有名なものに
源義家にまつわる物語がある。
義家が奥州平定のために北上した際、
馬の食料であった、ワラの俵に詰めた煮豆が
発酵し、糸を引くようになってしまった。
兵たちが捨てていた煮豆を、
まあ待て、と義家が食したところ、
十分食べられる食料であったため、
兵糧として採用した、というのが
そのストーリー。
糸を引く煮豆を
まず食した義家の勇気もさることながら、
それを食べさせられて戦った兵たちの心情は
いかばかりだっただろう。