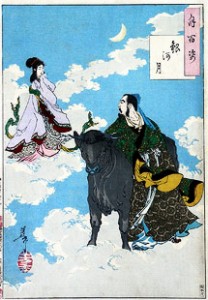「七夕の夜に」七夕の行事
今日は七夕。
旧暦で、七夕はお盆の7日目にあたる。
東北地方には、七草がゆならぬ、
「七たび飯を食べて七たび水につかる」行事があったという。
水を浴びるのは、体を清めるため。
この日に「井戸がえ」をする家もあった。
井戸の水をぜんぶさらって、お神酒を添えて、
いい水がわくように願った。
この日を「ネムリナガシ」と呼んでいる地方も多かった。
笹の葉に人の「眠り」をのせて、川へ流す。
青森の「ネブタ」も、「眠たさ」を流すことから
きたのかもしれない。
かつて、夏は眠くなる季節と考えられていたようだ。
七夕に水を使う行事は、涼しい夜を過ごすための
知恵だったのだろう。
今の熱帯夜にも使えそうだ。